日本のうまい酒10:長野、木曽の七笑
信州は、昔、信濃国10国からなっていた。
南から、伊那、筑摩、諏訪、小県、佐久、安曇、
更級、埴科、水内、高井。
その、地区ごとに、個性的な酒がある。
今回は、木曽義仲で有名な、木曽の酒・七笑を紹介しよう
信州木曽路に旨い酒あり
信州木曽路と言えば「夏でも寒い」と詠われるほど冷涼な地。
霊峰木曾御嶽山は真夏でも残雪をその頂きに置き、
木曽川の清流は手を切るほどに冷たい。
しかも、木曽谷深しと言われるように、七笑蔵のある木曽福島もまた、
谷間(たにあい)の町である。
昔から日本酒は、底冷えする木曽路には欠かせない「生活必需品」
であった。体の芯から暖まること・・・木曽に住む人々が、
めっぽう酒好きで酒豪が多いのも、ここの寒さを体験すれば、
なるほど・・・うなずける。
七笑酒造は明治25年創業。中山道沿いの宿場町である
「木曽福島宿」に誕生した。創業時の屋号は「藤新」ふじしん
初代蔵元、川合新助からその名を取った。
酒銘は「木曽錦(きそにしき)」《現在復刻商品あり》
と「七笑尾松(ななわらいおまつ)」である。
木曽福島は江戸時代から「難関な関所の町」として
栄えており、関所が廃止された明治時代も
訪れる人の数は絶えなかった。
昼なお暗い中山道の険しい山道を行く旅人達の
楽しみは、なんと言っても「旨し酒」。
・・・旅の苦労は旨し酒で、七回笑って吹き飛ばす。
木曽駒ケ岳からの伏流水が醸す七笑の酒は、先人の
心身にしみわたり、旅の疲れを癒したのだろう。
「七笑」名前の由来
「七笑(ななわらい)」の名前の由来は、さかのぼると
ひとつの地名に行き着く。
この地の歴史に残る「木曽義仲(きそよしなか)」は、
武士の始祖とも言われる豪傑。 源平合戦では見事に
勝利をあげ天皇から征夷大将軍を拝した有名な人物。
その義仲がまだ「駒王丸(こまおうまる)」と
呼ばれていた幼少のみぎりに、木曽駒の山奥に
自然児として過ごした美しい場所があった。
そこは、木曽川の源流木曽駒高原(きそこまこうげん)
に実在する「七笑」と言う名を持つ地籍だった。
屈しない強さを誇る木曽義仲が、最も大切にした場所
「七笑」には、さらにはこんな逸話もある。
青年となった彼は、なんとこの場所で、逢い引きをした。
と言うのだ。お相手が、かの「巴御前(ともえごぜん)」
であったかどうかは定かではないが、鬼神と詠われるほど
神がかった戦の天才「旭将軍・木曽義仲」の、なんとも
微笑ましくおおらかな一面をかいま見るようではないか。
生誕から850年を経た現在も、木曽義仲は
木曽路屈指の英雄である。
七笑酒造は、義仲の原点ともなった場所「七笑」の
ように、美しく清らか、豪快でおおらかな
日本酒の味の原点を、守り抜く姿勢で酒造りに
携わり続けている。
入魂の酒を醸す人々・・・
蒸し釜の湯気が冷気の中に立ちのぼる。
二月初旬午前六時、気温マイナス18度。まだ明けやらぬ
七笑蔵は見る間に熱気に包まれた。
今年初めての「大吟醸」の仕込みが始まる。張りつめた空気。
無心と言う言葉が一番近いだろうか・・・・
蔵人達からはいつも以上の真剣さが伝わってくる。
柳沢杜氏の無言の指示が蔵の空気を速やかに動かしてゆく。
かいがいしく働く蔵人達の無駄のない動き。高揚した頬、
吐く息の白さ。蒸し米のあら熱を取り、種付けがされる。
見事なほどの連係プレイ。麹室ではもうすでに数人の
蔵人が、次の作業を始めていた。
柳沢杜氏が決めたその日は、「大安吉日」。
いよいよ今年の大吟醸が搾られる。
蔵人達は朝から身を清め、新しい白衣に着替える。
昔からの製法「大吟醸袋しぼり」と、七笑自慢の
「槽しぼり(ふなしぼり)」。
二十年近く使われてきたという搾り袋は、丹念に
手入れをほどこされた愛用品の持つ風格さえ漂わせている。
やがて澄んだ音が、底冷えする蔵の中に響きわたる。
ゆっくりと醸されてゆく雫酒の芳香のまろやかさ。
まずは杜氏が利き酒をする。
・・・・静かにうなずく、笑みが漏れる。
見守る川合常務の元に利き猪口が渡され、
蔵人らと共にしぼりたての味を分かち合う。
斗瓶取りは10本。蔵の一番気のいい場所に置かれ、
静かに熟成の時を待つ。
「槽しぼり」は頭(かしら)を中心におこなわれる。
人一人が立てるほどの深い船の中に、逆立ちをする
ような姿勢で酒を入れた袋を敷き詰める。
一ミリの狂いもないほど正確に、袋取りの酒は船の中に
並べられて行く。その手際の良さ美しさ。
若い蔵人達は敬意を込めたまなざしで、頭(かしら)
の作業を自らの体にたたき込んでゆく。
酒は作り手に似るという・・・・
杜氏の顔を見れば、この蔵の酒の味がわかるのだという。
人間的な魅力と穏やかな包容力を兼ね備えた作り手
ならば蔵の気はあがり、酒は見事に微笑んでくれる。
酒造りは「祈り」に似ている・・・
柳沢杜氏と七人の蔵人の魂が融合されて七笑の酒は
生まれ出るのだ。
酒の神松尾様への祈り、七笑を支えてきた先人達の
祈り、森羅万象、八百万の神々への祈り。
そして霊峰木曽御嶽山を初めとする、この地の
自然に宿る神々の力と、木曽駒ケ岳から湧き出る
伏流水が、そんな入魂の酒造りを支えている。






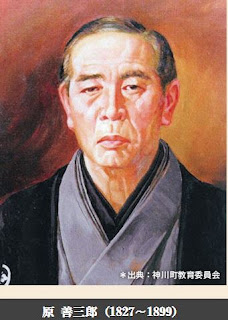
コメント