日本のうまい酒14:横笛(諏訪の五蔵)
横笛:伊東酒造(諏訪)
横笛の名前の由来は、『平家物語』の重盛に仕える若武者齋藤滝口時頼と
建礼門院の官女「横笛」との悲恋物語・横笛からきているという。
このようなお話を耳にした信仰心深かった初代当主が「横笛」の名を
後世に残すと同時に末長く菩薩を弔うことも含め、
『大銘酒 横笛』と命名し醸造することとなりました。
又、この悲恋物語を初代当主より耳にされた故伊東深水画伯は
当蔵の為に「紅梅の図」を図柄に描いて下さっております。
伊東酒造の日本酒について About Ito Brewery's Sake
タイプ別とすると、「フルーツのような香りがする」
「コメの香がする・味がする」「原酒で濃い」
「加水、アルコール調整をしてすっきりしたタイプ」
で商品をラインナップしています。
日本酒は同じお酒でも飲む温度帯で別のお酒になるので、自分の飲み方、
好きな温度を見つけてもらうと好きなお酒が見つかると思います。
杜氏が好む酒 吟醸酒「古道」
長野県の美山錦を55%精白の吟醸酒です。
長野県の酵母を使っているので、ちょっとフルーツのような香りがします。
味はちょっと多いタイプです。
常温で飲むか、ちょっと冷やして飲むか、
暑い時には氷を入れてロックで飲む。
アルコールが18%でも飲みにくさはないので、
女性のお客さんが多いです。
どんな料理に合いますか?
私は豆腐が好きなので、夏だったら冷ややっこだったり、
冬なら湯豆腐だったり、揚げ出しにしたり、
豆腐と合わせることが多いです。
(酒と豆腐の)両方を楽しめる気がします。
(日本酒の)材料自体はコメなので
「何かにダメ」ということは無いと思います。
ひやおろし三種へのこだわりについて
「米だけで作ったお酒で」「原酒で」「火入れは一回」
「純米大吟醸のひやおろし」と「純米吟醸のひやおろし」と
「純米酒のひやおろし」
「ちょっとフルーツのような香りがするタイプ」
「すっきりしたタイプ」「濃いタイプ」
3タイプ造るということは「それぞれタイプの違うものを造る」ということ
ひやおろしを始めた時から「原酒でやる」「火入れは1回しかしない」ということで、
これでずっとやっています。
純米系でやるのは
「お米の味と香りを楽しんでもらいたい」
「季節感を出す」ことが目的です。
「秋 穂の香」とか「冬 穂の香」などと必ず季節を乗せます。
基本的には「コメを感じてもらう」というコンセプトです。
このお米を「どのくらいのスピードで」「どのくらい溶かして」
「どんなタイプを造るか」
「お米の味をたくさん出して、米を感じてもらいたい」
というつもりで、
味わいが複雑で濃い純米酒、ひやおろしを造りたいです。
「すっきりしていて」とか、「香りが高くて」といった、純米吟醸系の
ようには造っていないです。
「純米酒を造るつもり」で造っているので
「(精米歩合)59%なので純米吟醸酒です」という考え方ではないです。
出来上がったお酒を貯蔵しておいて、
(ひやおろし解禁日の)9/9にラベルを張って
出荷をする前に試飲をしてみたら飲みにくいというときに
「全部タンクにあけてアルコール度数を15%に落として
もう1回瓶詰と火入れをして売ったらたくさん売れるからそうしよう」
という考えは基本的に無いです。
(そういうことはせず)「うちの純米のひやおろしはこれです」
ということでいきます。
杜氏の仕事とは:「微生物がお米を日本酒に変えている」
というところでは、「非常に神秘的で面白そう」
というイメージを持たれます。
現実的には、寒い時期に水仕事で、重いお米を扱って、
当然衛生面では使う道具を洗って殺菌して使って、
また洗って殺菌して元に戻す。
こういったことの繰り返しなので、
傍から見るのとは違って、非常に重労働というところはあります。
毎年同じお米、同じ精米をされたものでも性質が違ったりするので
その辺の工夫をどうやってやるかなどは、
面白味であったり、苦しみであったりというところはありますね。
どういう香りで、どういう味に作るか?という点は、
仕入れたお米を、どのくらいのスピードで、
どのくらいお酒にするかというところで酒質が決まってくるので、
「米の性質をいかに活かせるか」を年によって工夫をしながら、
チャレンジな感じはしますけれど。









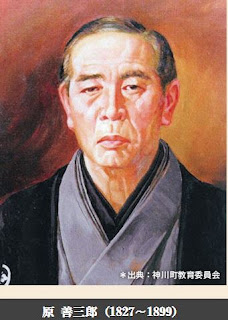
コメント