日本のうまい酒7,新潟・魚沼の銘酒:八海山
新潟に転勤し、仕事で、小出、六日町方面を担当しており、
八海山の名前を知ったのです。
ただ、越乃寒梅、雪中梅もそうですが、八海山も、
そう簡単には買えないのです。
地元の酒屋さんと、仲良くなって、月に1本なら売るよ、
とか言ってくれるようになるのです。
多くは、入荷したら電話するとか、15日過ぎに、電話して
在庫あれば売るとか、酒屋さんの都合にあわせることになるのです。
がめつい酒屋は、他の酒、3本買えば、銘酒を1本つけるとか
言う所もあるくらいです。
そんな調子で新潟に住んでいて直接酒屋に買いに行くのでも、
銘酒は、月に一升瓶1本程度しか手に入らなかったのです。
そう言う銘酒は、越乃寒梅、雪中梅、八海山、久保田萬壽以上の製品、
などがありました。
八海山のホームページ
http://www.hakkaisan.co.jp/
八海山の環境と麹、酒の特長
新潟県南部に広がる魚沼地方は、霊峰・八海山を臨む、
自然に抱かれた美しい地域です。
冬は背丈を超すほどの深い雪に覆われますが、春になれば雪解け水が
豊富な伏流水となり、田畑を潤します。
そこから生まれるのが日本一美味しいコシヒカリ。
さらに魚沼の風土は「越後上布」などの伝統織物や淡麗な日本酒、
独特の食文化も育んできました。
雪の恵みともいえる美しい手業や味わい。
雪国の暮らしは時に厳しさもありますが魚沼の人々は雪をプラスにし、
知恵と工夫で豊かな冬の暮らしを営んできました。
農作業のできない冬は、雪のお布団が土をゆっくり眠らせてくれる。
そう思いながら、春の訪れを待つのです。
陽の光が温もりを増してくると大地はざわざわと鼓動を始め、
一斉に芽吹きの時を迎えます。待ちこがれた春の到来です。
雪国の春はひときわ美しく、躍動感にあふれます。
野山は新緑にきらめき、次から次へと山菜が顔を出します。
フキノトウ、コゴミ、ワラビ、ゼンマイ、タケノコ・・・
この時季にしか味わえない大地の息吹が食卓を賑わせます。
色とりどりの花の競演も始まります。淡い色が重なり、
やさしい風情を奏でる雪国の春。
長い冬を過ごしたからこそ心が躍る、歓びに満ちた季節です。
日に日に緑が深まり、魚沼盆地は蒸し暑い夏を迎えます。
清流・魚野川ではアユやイワナなどの魚たちが銀鱗をきらめかせます。
魚がたくさん棲むところ、という「魚沼」の地名は、
そんなところから付いたのかもしれません。
畑ではたっぷりの陽を浴びて、野菜がぐんぐん育ちます。
真っ赤な神楽南蛮、つやつやとした巾着なすなどの
伝統野菜やさまざまな夏野菜がたわわに実り、
冬に備えた保存食づくりも忙しくなります。
空が澄み、秋風が吹き始めると、大地は黄金色に染まり、
いよいよ美味しいお米の収穫です。
秋の訪れとともに、山頂から赤や黄色に色づき始め、
山々は美しく粧いを変えていきます。
錦繍に染まるあでやかな姿。
燃え立つ風情が心に染み入ります。秋の恵みは豊富なきのこや
秋野菜。収穫の喜びに沸いた後は、ひと雨ごとに寒さが深まり、
冬が駆け足でやってきます。
やがて雪が舞い降りて、魚沼の地は真っ白な銀世界に。
しんしんと降り積む深い雪が、大地を
再び静かに眠らせます。
酒蔵の麹の特徴とは?
全酒類に手造りの「突破精麹」を使用
酒造りの命ともいえる麹。その最大の特徴は麹菌の菌糸の
生え方です。
蒸した米に麹菌が生えることを破精(はぜ)るといいますが、
最高の日本酒を造り出すのは「突破精麹」です。破精には、
下記のようなものがあります。
酒蔵の麹 突破精麹 米のところどころに菌糸が生え、
内部にも深く食い込んでいる。
日本酒の吟醸・大吟醸など高級酒はだいたいこの麹を使う。
何度も手入れし、人の手による厳格で緻密なコントロールが
必要とされる。手作業でなければ絶対に造れない麹。
八海山では麹造りは全て人間の手作業で行われています。
そして全てのお酒にこの突破精麹を使用。
その他の麹 総破精麹 米全体に菌糸が生え、表面も内部も
菌糸で覆われている。味噌などはこの麹を使うことも多い。
ヌリ破精麹 米の表面だけに菌糸が生えた状態で内部に
米の芯が残っている。
特徴1 雑味がなくすっきり
酒米は、雑味となるタンパク質や脂肪分を取り除くために
精米します。
八海山の精米歩合は、普通酒で60%、大吟醸では40%と
削る割合が高いため、雑味がなくすっきりとした
上品な味わいになります。
特徴2 自然な甘み
突破精麹は、デンプンをブドウ糖に分解するアミラーゼという酵素の
力が強いため甘みが増しますが、それは砂糖とは違う自然な甘み。
ブドウ糖は体へも消化吸収しやすく、脳のエネルギーになります。
特徴3 素材を活かした料理に
突破精麹は、麹菌の増殖が控えめなのでカビ臭さがなく、
浅漬けなど麹の味が出やすい料理に最適です。
生で食べる食材を、より繊細に美味しくします。
八海山の麹造り
理想の酒を造るために、 最高の麹を造る
全ての酒造りに大吟醸酒の造りを応用する。
それが八海山のポリシーです。
その姿勢は麹造りにも貫かれています。
酒造りは、昔から「一に麹、二に酒母、三にもろみ」と
言われるように、酒質を決める最も重要なものが麹です。
目指す品質の麹を造るには、精米から洗米、吸水、
蒸し加減、温度管理など、全ての作業に細かく
気を配らねばなりません。麹は生き物ですから自然の力に
委ねられてはいますが、ひとつひとつの作業に最善を尽くし、
見て、触って、香りを嗅ぎながら、
杜氏と蔵人が一体となって最高の麹造りに努めます。
麹造りの心構え
酒造りは、最高責任者である杜氏を中心に、
蔵人たちの手によって行われます。
生き物を扱う仕事ですから、24時間傍を離れられない事も多く、
仕込みの時期は、まるで家族のように寝食を共にします。
酒造りに一番大事なのは人。いいものづくりには、
その人の人間性が反映されます。
周りから信頼を得て認められるには、鋭い感覚を持ち、
酒に対しての真摯な想いがあり、
素直に忠実に黙々と、自分のやるべきことを続けられる
姿勢が求められます。近代的な世の中になっても、
機械は到底人間の感覚には及びません。
いい酒造りには、やはり人の手が欠かせないのです。
その中でも麹造りはベースとなる重要な作業。
見えない微生物を相手に蔵人が一丸となって
目指す麹を造る。
そこには、理想の味に向かってひたむきに突き進む、
蔵人たちの揺るぎない心と誇りが秘められています。
(八海山の情報を参照させていただきました。)







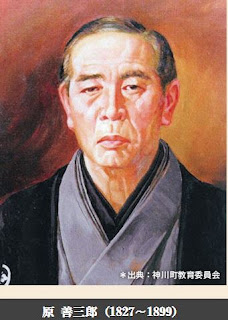
コメント