日本のうまい酒8:加賀の老舗の菊姫について
味は、飲みやすさと言うよりも、男酒、ガツンとくる感じ
重厚感ある、飲み応えある酒という感じ
重厚感ある、飲み応えある酒という感じ
「菊姫」はその伝統を今に伝えるため、「菊酒」、
「菊理媛」(白山比咩神社御祭神)にあやかり
命名されたと伝えられている。
日本で初めてのメーカーを目指して:
宣伝文句に「秘伝の」とか「伝統の」とか、日本酒は神秘性を
持たせたほうが商売がしやすいという傾向があります。
消費者のほうが潜在的に神秘性を求めているからです。
しかし、極端に言えば、日本酒も物理・科学の世界です。
宇宙遊泳を終えて帰還できるのも、コンピュータが
計算してくれるからであって、決して勘ではありません。
菊姫が着手していること。それは杜氏がもつ優れた技術や
勘を徹底的に分析・データ化し、企業ノウハウとして
蓄積することです。
ここにおいてのノウハウとは造りかたの詳細な「設計図」
や判断を企業の側が持つということであって、
単純に機械化・コンピュータ化を押し進めるという
ことではありません。
したがって、菊姫では大手酒造メーカーなどの
ように工業製品としての酒造りを目指している
のではなく、最高の材料と人間の感性を生かした
酒造りを続けていきたいと考えています。
なぜならば、酒が嗜好品であるからこそ、人間の
五感を最大限に生かした酒造りをしていきたいのです。
このことは神秘性とは無縁の話です。
菊姫は本来の意味において、「日本で初めての」
日本酒メーカーを目指しています。
それは着実に手ごたえとして、感じつつあります。
菊姫は、山田錦の産地のなかでも特に評価が高い
特A地域の兵庫県三木市吉川町に「村米」という
栽培契約地区を持ち、高品質の山田錦を安定して
入手しています。 菊姫の吟醸酒・純米酒には、
全て山田錦を100%使用しています。
また菊姫では、普通酒においても酒造好適米を使用して
います。中でも、「淳」は日本で初めて
山田錦を100%使用した普通酒として高い評価をいただいております。
菊姫は、今後も良質の原料米を使用することにこだわり続けます。
そして、それが良い酒を造るための基本であると考えています。
これほど山田錦が脚光を浴びる二十年ほど前から
日本一の山田錦の生産地として名高い兵庫県美嚢郡吉川町
に菊姫は足しげく通いつめてきました。
当時、値段の高い山田錦は他メーカーが手を出し
にくくなっており、また菊姫側の熱心さが通じ、
何とか三〇〇俵を入手すること ができました。
それが吉川と菊姫の繋がりの第一歩でした。そして現在、
吉川町の全生産量の 約1/4に相当する一万俵を菊姫は
毎年確保 しています。この数字は単なる契約栽培を超え、
生産者との信頼関係が築かれてきたことを物語っています。
その交流会が自然発生的に生まれた「姫と語る会」です。
吉川町は「村米制度」と言って、生産する側とそれを買い付 ける
蔵元が一体となって酒米作りを育んできた長い伝統を誇る地域。
農家の生活を保障するとともに品質の良い酒米を二人三脚で
育てあげてきた歴史があります。
吉川は生産地として「特A」のなかでも、さらに最高ランクに
位置する「特AAA」指定されている山田錦の里。
「姫と語る会」のメンバーは、この吉川の七つの集落、
吉安上地区(きちやすかみ)、吉安下地区(きちやすしも)、
大沢地区(おおそ)、米田地区(よね だ)、 鍛治屋地区(かじや)、
貸潮地区(かしお)、 山ノ上地区(やまのうえ)の
篤農家の皆さんと菊姫の間によって構成され ています。
手造り優先のためのハイテク
たとえそれが非効率なことであっても
菊姫の平成蔵は業界最新のハイテク設備を擁していますが、
それら全ては「手造り」を最優先させる考え方が貫かれています。
たとえば、もろみ温度の計測や麹室の温度・湿度管理は
24時間コンピュータの監視の下に置かれています。
これらは、人間のうっかりミスを防ぐためには大変便利な
道具ですが、
その後の判断と対処こそが重要な人間の仕事だと考えています。
つまり、ハイテクは最高の手造りをするためのバックアップの
役目を果たしているにすぎません。
特に原料処理における洗米・浸漬の作業は大変デリケートなので、
平成蔵でも機械化せず手作業で行います。また、麹室も他に
例を見ないほど広いスペースを確保していることもその表われです。
ここは麹蓋による完全手造りの製麹を行うため、人間工学に基づき
特別に設計された室で、均一な薄さで蒸米を広げることができるよう、
たっぷりとした広さを誇っています。ここでは大きな1つの部屋を
4つに仕切り、状況に応じてそれぞれの部屋を独立させたり、
つなげたりすることができる菊姫独自の工夫が擬らされている
ことも特徴です。
ハイテク
仕込みタンクはもろみの醗酵温度の変化に迅速に対処できるよう、
小さな特注3重ジャケット構造のタンクを使用しています。
これも人間が丹念に目が行き届く範囲の作業を菊姫が
最も大切だと考えていることの一例です。
つまり、非効率的であったとしても、品質に優しいことを
いかなる時も主眼に置いています。
それは反面、人間に厳しさを要求します。
しかし、最高の手造りを行うために、今後も菊姫は
単なる大量生産のための省力化は決して行いません。
精米後の「枯らし」を重視
枯らし:吟醸酒造りに力を注げば注ぐほど、精米機はフル稼動状態
となり、処理能力が目一杯となってしまいます。
それでも、これを他に委ねないもう一つの理由は、
菊姫では「枯らし」を重視しているからです。
これは品温を静かに落とし、米自体が含んでいる水分量を
一定期間置くことで10%から13~14%に戻す効果があります。
こうした水分の平均化・ 調節の工程は次に続く洗米時、
急激な吸水で米が割れないとうにするためです。
精魂込めて生産者が育てた酒米、それも極上の山田錦を
可能な限り丹念に時間をかけて磨いたり、「枯らし」の
期間をしっかり計算して行う工程を果たしてどこが
やってくれるでしょうか。
これを実現するには完全自家精米しかあり得ないと
菊姫では考えています。
八基の精米機で万全の準備
従来、旧精米所にて四基の精米機で精米を行っていたが、
新精米工場(八幡工場-やはた) の落成とともに新たに四基が
加わり計八基での稼動が実現しました。
これにより、充分に余裕を持たせた精米を行うことが
可能となったのです。
菊姫は「精米を他所に頼むようなら、酒造りを止めろ」という







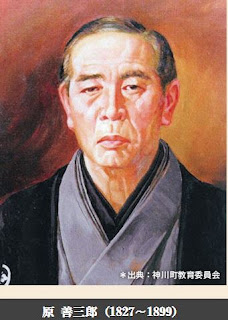
コメント