日本の旨い酒17:真野鶴(佐渡)きれいで、すごい、醸造所の娘がいた。

日本に、きれいで、すごい、醸造所の娘がいた。
その名は、尾畑留美子。佐渡の真野鶴醸造所
https://www.obata-shuzo.com/home/ (真野鶴醸造所 )
「真野鶴」五代目蔵元。
1965年、佐渡の「真野鶴」蔵元の二女として生まれる。
佐渡高校、慶応大学法学部卒業。
大学卒業後は、東京に残り日本ヘラルド映画(当時)の宣伝部に所属。
ハリウッド映画「氷の微笑」「レオン」などの宣伝プロデュースを担当。
1995年、角川書店「Tokyo Walker」編集者(現:弊社社長)
と結婚し、故郷の蔵を継ぐ。
現在、尾畑酒造・専務取締役。二女の母。
2014年から佐渡の廃校を仕込み蔵として再生させた
「学校蔵プロジェクト」をスタート。
2017年5月『Forbes Japan』により「ローカルイノベーター55人」
に選ばれる。
きき酒マイスター(公益財団法人日本醸造協会主催)
日本酒造組合中央会・需要開発委員
農水省食料・農業・農村政策審議会臨時委員
著書『学校蔵の特別授業~佐渡から考える島国ニッポンの未来』
(2015年11月24日発刊、日経BP社)
WEBマガジン『Byron』にて日本酒コラム連載中
佐渡・真野・真野鶴 米:佐渡は日本一の米どころである新潟県の中にあっ て魚沼と並ぶ稲作地として知られています。そんな最高の稲作地である佐渡の中でも「真野鶴」が契約する農家は小佐渡山脈の麓に位置する旧羽茂町の山間部にあり、俗に言う“山付きの米”が穫れます。 “山付きの米”は冷たい清水で育つため収穫量は少ないのですが、その品質は平野部のものより一段高いと言われます。もちろん、そこで穫れる酒造好適米・五百万石も高いレベル。また近年では山田錦を母に五百万石を父に持つ新潟県が開発した新酒米「越端麗」を蔵人中心に栽培を開始しました。こうして得た良質の米の恩恵を受けて、毎年「真野鶴」は醸し出されています。
水:周囲250km、東京23区の約1.5倍の広さがある佐渡。
北には大佐渡山脈が、南には小佐渡山脈が連なり、毎年冬になると
山々は白く染まります。大陸から日本海を越えてやって来る寒波がもたらす雪は、新潟の他 地域に比べ大地がもたらす様々な影響を
一切受けないため限り無く鮮度が高く、その雪解け水が地中深く
染み込み、自然のろ過の恩恵により山の麓に湧き出す際 は清冽を極めます。
「真野鶴」のある真野町は島内の中でも水量・質ともに高いことで
知られ、そのため古来より佐渡国分寺が建立され国府として栄えた
歴史をもっています。
また、佐渡島内6醸造場のうち3場が真野町に集中していることから、
この町の水質の良さが伺えます。もともと良い水質に加えて、「真野鶴」
はより深い井 戸から、より良い水をとの考えから、仕込み水に地中70m
より湧き出す地下水を使用。その水質は新潟県の特徴ともいえる軟水であり、淡麗で口当たりの柔らか な酒を醸すのに最適な材料となっています。
人=杜氏:「真野鶴」は人=杜氏においても恵まれています。
現在の杜氏・工藤賢也は昭和46年生まれという若さながら、
大学卒業後、前杜氏・松井万穂に弟子入りし、その実績において県内屈指で、全国の杜氏の中でもトップクラスの実力をもつ松井杜氏より技術を
伝授されました。
平成12年秋に29歳という若さで尾畑酒造の杜氏に就任して以来、
最近では大半の蔵で合理化のため廃止されてしまった冬期間無休の
蔵人泊まり込みによる早朝仕込みを実践。
これは島内唯一で、 寒い冬の間でもより温度の低い早朝に仕込みを行い、
少しでもいい酒を醸し出そうという強い姿勢の現れといえます。
近年、機械化が進む中、手間隙を惜しまず頑なに“手造り”を守り続けるのが「真野鶴」の、そして工藤杜氏の最大のこだわりです。
こうした姿勢は国内外での評価にも結び付き、6年連続して
全国新酒品鑑評会「金賞」受賞。
また毎年ロンドンで開催されている世界最大のワインコンテストである
インターナショナル・ワイン・チャレンジにて2007年に新設された
日本酒部門で228点中11点という難関を突破してゴールドメダルに
輝くなど数々の実績を残しています。
学校蔵について:学校蔵とは、佐渡にある廃校を仕込み蔵として再生した
場所で、2014年から稼働。「学校蔵」を製造。
ここでは夏場に酒造りをしており、「酒造り」「学び」「環境」「交流」の4つの柱で運営している。
夏にオール佐渡産の酒米で仕込みを実施。仕込みタンク1本につき
1期一週間の学び期間を設けて、仕込み体験希望者を受け入れている
(人数に制限あり。本年度の募集は終了)。
酒造りのエネルギーも佐渡産を目指し、東京大学IR3Sとの
共同プロジェクトの一環で太陽光パネルを設置し、電気に関しては
理論上100%自然再生エネルギーを導入している。
様々な企業や組織、学校とのコラボレーションワークショップを実施。
特に毎年6月に開催している「学校蔵の特別授業」では
多くの参加者が集う。2017年からは酒蔵センシングこと酒蔵ロボット
「モロミ君」を導入。
「モロミ君」は酒の知識を勉強して、学びに参加する生徒との
コミュニケーションツールとして活躍する予定。
注:免許の関係でリキュール表記









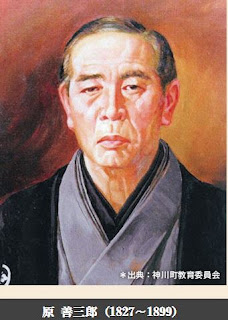
コメント